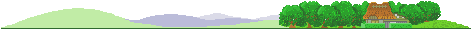笠松町米野640
池田輝政ら1万8千の東軍は、旧暦8月22日の朝、川を渡って米野へ上陸し、次の日岐阜城を攻め落とした。
この戦い跡(現在は町の墓苑)には石碑と詩碑があり、笠松町指定文化財(史跡)となっています。
<父親の墓もこの地にあります。>
 米野の戦い跡
米野の戦い跡
笠松町江川
無動寺地先堤外
直径30cmから1mほどの葉を広げ、8月から10月にかけ直径4、5cmほどの紫色の花を咲かせます。
スイレン科で、葉に多数のとげがあるのが特徴。
絶滅危うぐ種として環境庁のレッドデータブックに記載され、県内では海津町と笠松町の2カ所だけです。
スポ−ツ交流館
笠松町江川116番地
この建物は、エアロビクス、ジャズダンスなどのフィットネスのほか学習や集会の場として、また、木曽川河川敷内の運動場利用の際の休憩、打合せの場として利用いただけます。
笠松町江川
無動寺地先堤外
この池は古い川筋が残って池になった、全国でも数少ない河跡湖として地形的にも珍しいです。
この池では珍しい「ベッコウトンボ」や県内で初めて「アズマオトメマイマイ」というカタツムリが発見されました。
笠松町無動寺225
光得寺
この、梵鐘は、鐘形よく整い、その音色も優れ、室町風の代表的なものとして昭和40年6月、岐阜県重要文化財(工芸品)に指定されました。
専養寺のイチョウ
笠松町円城寺
芭蕉踊り
笠松町円城寺919
毎年8月22日に秋葉神社へこの祭りが奉納され、平成元年11月、岐阜県重要無形文化財に指定されました。