| 巡礼街道ガイドマップ |
| | 史 跡 等 | 説 明 |
| 1 | 木接太夫彰徳碑 |
平安時代から、代々坂上家が花木の継承、発展をさせていった。安土桃山時代に坂上善太夫が、接木の技術に優れていたため、豊臣秀吉から「接木太夫」の称号を与えられ、それを顕彰して建てられたもの。現在植木のまち、山本のシンボルになっている。
 接ぎ木の発明者「木接太夫」 接ぎ木の発明者「木接太夫」 |
| 2 | 松尾神社 |
数百年の歴史を持ち、京都の松尾大社と縁が深く、大社の分霊をワラ神輿で京都の桂川から流れたものが、天正時代から続く「トントコ祭」の起源で、その行事が行われていたが、形を変えて復活した。祭神は坂上田村麻呂。社殿は一間社流造りで市指定文化財。
 「たからづか時空往来」(松尾神社) 「たからづか時空往来」(松尾神社)
 「たからづか時空往来」(トントコ祭) 「たからづか時空往来」(トントコ祭)
|
| 3 | 山本園芸流通センター |
園芸の盛んな山本で観賞用の牡丹が育培され、元禄時代にはその種類は百種を超えた。現在日本一を誇る須賀川市の牡丹園の起こりは、18世紀に山本から薬種牡丹を購入したのが始まりで、平成5年にこの縁で牡丹の古木が里帰りしたものが植えられている。
 宝塚植木まつり 宝塚植木まつり |
| 4 | 泉流寺 |
土地の人に「眠り観音」と親しまれ、眠りに関する悩みや、病気で苦しむ人たちを救ってくれる観音さま。北摂の名刹だったが、江戸時代観音堂を残して全てが消失してしまった。のち加賀前田家の人が再建して、一時格式も高まった。本尊は市指定文化財。 |
| 5 | 正念寺 |
明治14年まで念仏専修道場であった。元禄時代に山本の富豪坂上輿次右衛門が、名妓吾妻太夫を寵愛。輿次右衛門没後、吾妻太夫は尼となり、菩提を弔いつつ、道ゆく人に湯茶を接待したという。庵室は茶所と呼ばれ、親しまれたが、昭和30年撤去された。 |
| 6 | 行基のなげ石 |
行基が「街道筋にあった通行に邪魔な岩を投げとばしたもの」といわれる。傍らに30mの巨木のイチイガシがある。 |
| 7 | 天満神社 |
一間社春日造りの柿葺きの小さな社で、元禄10年に再建された記録がある。祭神は菅原道真で、「トントコ祭」は昭和38年まではずっと行われていた。 |
| 8 | しだれ桜 |
天神川沿いに見事な2本のしだれ桜があるが、正式には平安桜という。樹齢55年といわれているが、桜の季節には道ゆく人の目を楽しませてくれる。
1999年5月、宝塚まちなみデザイン賞・建築物部門受賞
 しだれ桜・中筋山手四丁目 しだれ桜・中筋山手四丁目
|
| 9 | 中山寺 |
 宝塚市の寺院 宝塚市の寺院 |
| 10 | 中山寺の梅林 |
境内の続きの裏山が梅林だが、山の傾斜に春を告げるみごとな梅の群生がある。2月下旬〜3月初旬が観梅の盛期である。 |
| 11 | 足洗川と勅使川 |
聖徳太子の時代、太子の馬の足を洗ったとされる足洗川。また、用明天皇の勅使が渡ったとされる勅使川には今もその名が残る。 |
| 12 | 市杵島姫神社 |
祭神は市杵島姫命で、もとは中山寺の寺域にあったものを明治4年に、この地に移されたものだが、慶長8年(1603)創建のものである。 |
| 13 | 菰池周辺 |
長尾連山を背景に菰池沿いに桜並木が続く。視野が広がり、ホットする場所。 |
| 14 | 黙想の家 |
売布神社の森林道を通り抜けると、静かなたたずまいの中に黙想の家がある。こんもりとした庭内を入ったところには、キリストの彫像がある。 |
| 15 | 売布神社 |
 宝塚市の寺院 宝塚市の寺院
 「たからづか時空往来」(売布神社) 「たからづか時空往来」(売布神社)
|
| 16 | 旧橋本関雪邸 |
明治から昭和初期に活躍した日本画家の別邸。関雪は明石に生まれ、四条派の手ほどきをうけ、四条派南画の手法を加えた独特の絵で、好んで動物を書いた。庭内には多くの石仏や塔があり、「冬花(瓜)庵」と名付けられている。 |
| 17 | 鉄斎美術館 |
清荒神本堂の奥に、幕末から大正にかけて活躍した南画家富岡鉄斎の作品が常設展示されている。清澄寺法主と交遊があったため、作品の収集と美術館開設となった。
 鉄斎美術館案内 鉄斎美術館案内 |
| 18 | 清荒神清澄寺 |
 宝塚市の寺院(清荒神) 宝塚市の寺院(清荒神)
 「たからづか時空往来」(清荒神清澄寺) 「たからづか時空往来」(清荒神清澄寺)
|


 写真による案内
写真による案内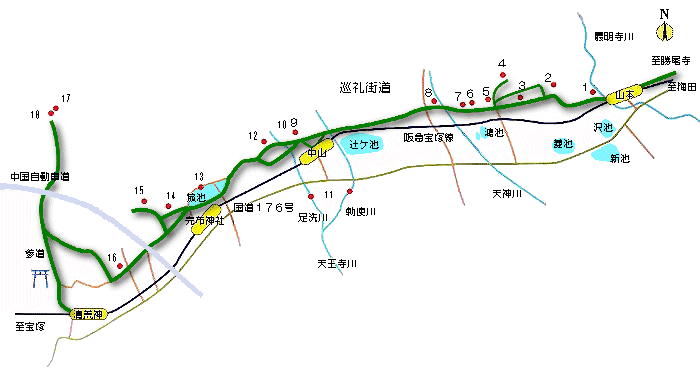
 接ぎ木の発明者「木接太夫」
接ぎ木の発明者「木接太夫」 「たからづか時空往来」(松尾神社)
「たからづか時空往来」(松尾神社) 「たからづか時空往来」(トントコ祭)
「たからづか時空往来」(トントコ祭)
 宝塚植木まつり
宝塚植木まつり しだれ桜・中筋山手四丁目
しだれ桜・中筋山手四丁目
 宝塚市の寺院
宝塚市の寺院 宝塚市の寺院
宝塚市の寺院 「たからづか時空往来」(売布神社)
「たからづか時空往来」(売布神社) 鉄斎美術館案内
鉄斎美術館案内 宝塚市の寺院(清荒神)
宝塚市の寺院(清荒神) 「たからづか時空往来」(清荒神清澄寺)
「たからづか時空往来」(清荒神清澄寺)
 祭神は応神天皇。震災後再建されたが、向拝、宝珠柱等に特色のある本殿は国の重要文化財指定。
祭神は応神天皇。震災後再建されたが、向拝、宝珠柱等に特色のある本殿は国の重要文化財指定。 宝塚の寺院(八幡神社)
宝塚の寺院(八幡神社)
 中山寺の催しもの
中山寺の催しもの


 TopPage
TopPage